LaTeXで論文を書いた2025/07/24(木)
先日、「投稿論文を LaTeX で書き直す」という記事を書きました。その時は、せっかく書き直したのに結局使われなかった、という悲しいオチになったのですが、LaTeX で化学論文を書くことに一定の手応えは感じました。そこで、頑張って新しい論文を一から LaTeX で書いてみました。プレプリントとして公開しています(DOI:10.26434/chemrxiv-2025-k8jhs)。
お前は LaTeX を使うために論文書いとんのか?手段と目的が逆転しとらんか??と激詰めされそうですが、実のところ、私は昔からそういう気配がないでもないのです。大学院生のとき、まだ Windows が存在してなくて Mac が高嶺の花だった時代、私は「論文を書くのと平行して自作のワープロソフトを開発する」というアホみたいな活動をしておりました。当時使っていたパソコンはシャープの X68000 で、「ただのゲームマシンだ」とバカにする人も多かったのですが、当時これほどプログラム開発に適したマシンはそうそうなかったのです。結局、給料をいただく身分になって Mac を購入した後は、その自作ソフトは全く出番がなくなり消えてしまいましたが、それを使って書いた論文はちゃんと残っています。閑話休題。
さて、1本論文を書いてみると、いろいろ気づくことが出てきます。
- 参考文献の管理はめちゃくちゃ楽。途中で参考文献を増やしても、番号のつけ直しが全く必要ない。Word の脚注機能でも一応できるのだけど、同じ論文を2箇所で引用するときが面倒。また、Word の内部で脚注の情報がどのように管理されているのか、イマイチわかりづらく、不安が大きい。(経験上、このように複雑な内部構造を持つデータは、プログラムの不具合でデータ消失のトラブルが起きやすい。LaTeX のデータは単純なテキストファイルなので、原因不明のデータ消失が起きる確率は極めて低い。)
- 化学式は
\ce{...}で書く。下付きなども自動的に処理してくれるので非常に楽。 - 指定した幅に収めてくれるはずなのだが、ときどき職務放棄して派手にはみ出すことがある。
ハイフンを含む単語の途中で改行できないからだと思うのですが、長い化合物名が文中に出てくると、この現象が高い確率で起きてしまいます。強制的に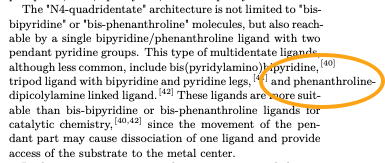
\linebreakを入れて対処してるんだけど、そんなもんなんかな? もう少し合理的な方法ないんですかね?? lualatex,pbibtex,lualatex,lualatexの順に走らせること。pbibtexの後にもう一度lualatexを走らせないといけないのはわかっていたのですが、さらにもう一度走らせないと、図の番号が正しく振られないみたいです。- PDF を作るのに要する時間は、2カラム8ページ程度の論文で、30秒ほどでした。まあこの程度なら、十分待てるかな、と思います。
今回の論文の内容については、まだいろいろ技術的に詰めないといけないところが残っています。合成の再現性を確かめるとか、元素分析を合わせるとか(ため息)。合成化学の論文は、ここのハードルが高いんですよね……ぼちぼち進めていきます。

