ChatGPT は受験勉強を時代遅れにするか?2023/02/22(水)
ABEMA Times で「『ChatGPT』は試験やレポートに活用すべき? 『AIがある前提で問いを立てる、出題側のセンスの課題になる』(慶應大・宮田教授)」という記事が出ています。何かの参考になるかなと思って、動画を見てきました。
まず、受験勉強が「今までは1人で知識を一生懸命習得して、与えられた問いに対して答えを出すものだった」とされていますが、この認識がそもそもずれている気がします。受験勉強というのは、それ自体が目標ではなくて、「答えを出すことができるようになるプロセス」に意味があるのです。入学試験が「知識を習得して、問いに対して答えを出す」ことに限定されているのは、「高校卒業程度」の発達段階に合わせて目標設定しているだけの話です。
「それはChatGPTで全部できてしまう」とのことですが、本当でしょうか。試しに、「アルケンの求電子付加反応」(こればっかり)について ChatGPT に聞いてみました。
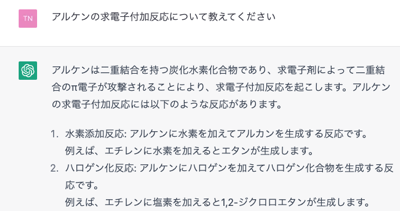
「水素添加反応」! さっそくダメじゃん。まあ学習が不十分だったんだろう、と大目に見てあげることにしましょう。ちょっと意地悪なダメ出しをしてみます。
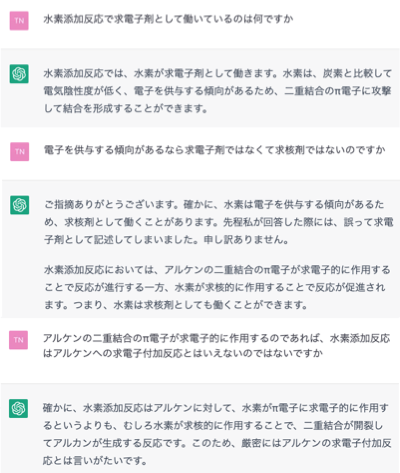
なんかすごく既視感のある会話だな。「勉強はしてないけど口だけは回る」残念な学生との会話にそっくりだ。要するに「知識が足りてないからそれらしくごまかしている」わけです。ただし、今後知識を増やしていけば、「アルケンの求電子付加反応について述べよ」という程度の問題に対しては、初手から満点の回答を出せそうな感触はありますね。
仮に、「知識を組み合わせて答えを出す」段階を、それが得意な ChatGPT などに任せるとしましょう。問題は、人間がこの段階を飛ばして、いきなり「それよりもさらに高度な部分」を担う段階に到達できるのか、ということになります。この点について、私はかなり懐疑的です。最初の段階を自分で踏んでいない人が、いくら機械の助けを借りるといっても、その次の段階に進んでいくことができるものだろうか。さらに、上のように ChatGPT が「知識が足りないところをごまかして」いるときに、おかしいと気づくことができるかどうか。そのためには、自分で原典に当たって確かめる必要があるでしょう。つまり、「知識を組み合わせて答えを出す」ことは、結局人間にも求められるのではないか、と思うのです。
私は、ChatGPT などの人工知能が発達しても、自分で勉強することの意義は全く薄れないし、むしろ必要性が高まるのではないかと考えています。そもそも、人間が生きていくためには、社会の中で何らかの役割(会社で働くとか)を果たさなくてはなりません。ある種の役割は人工知能が肩代わりしてくれるでしょうけど、多くの場合は「人工知能の助けを借りて人間が役割を果たす」ことになります。その時の人間は、主体的に考えて行動し、時には人工知能の誤りを正す能力を持たねばなりません。そして、「主体的に考える」という段階には、いきなり到達することはできない。その前に、「知識を組み合わせて答えを出す」段階を通る必要があります。地道な努力が嫌いな人には辛い結論かもしれませんが、これが現実だと思います。

